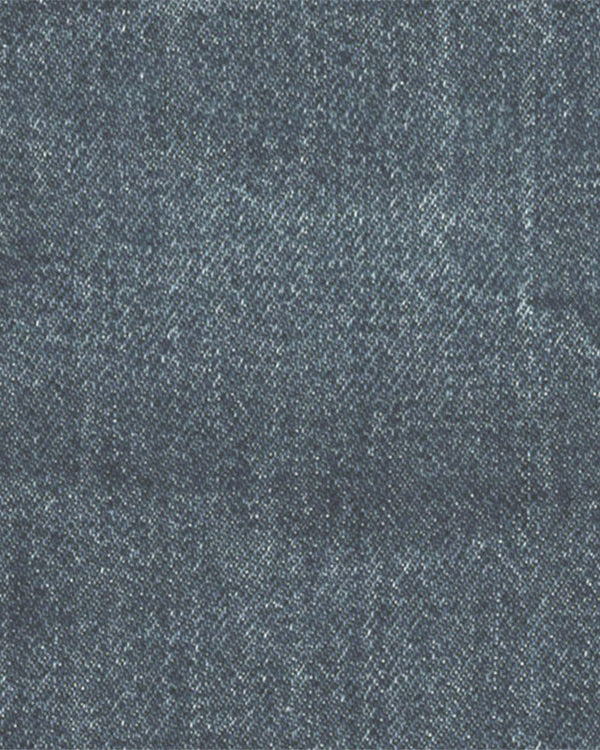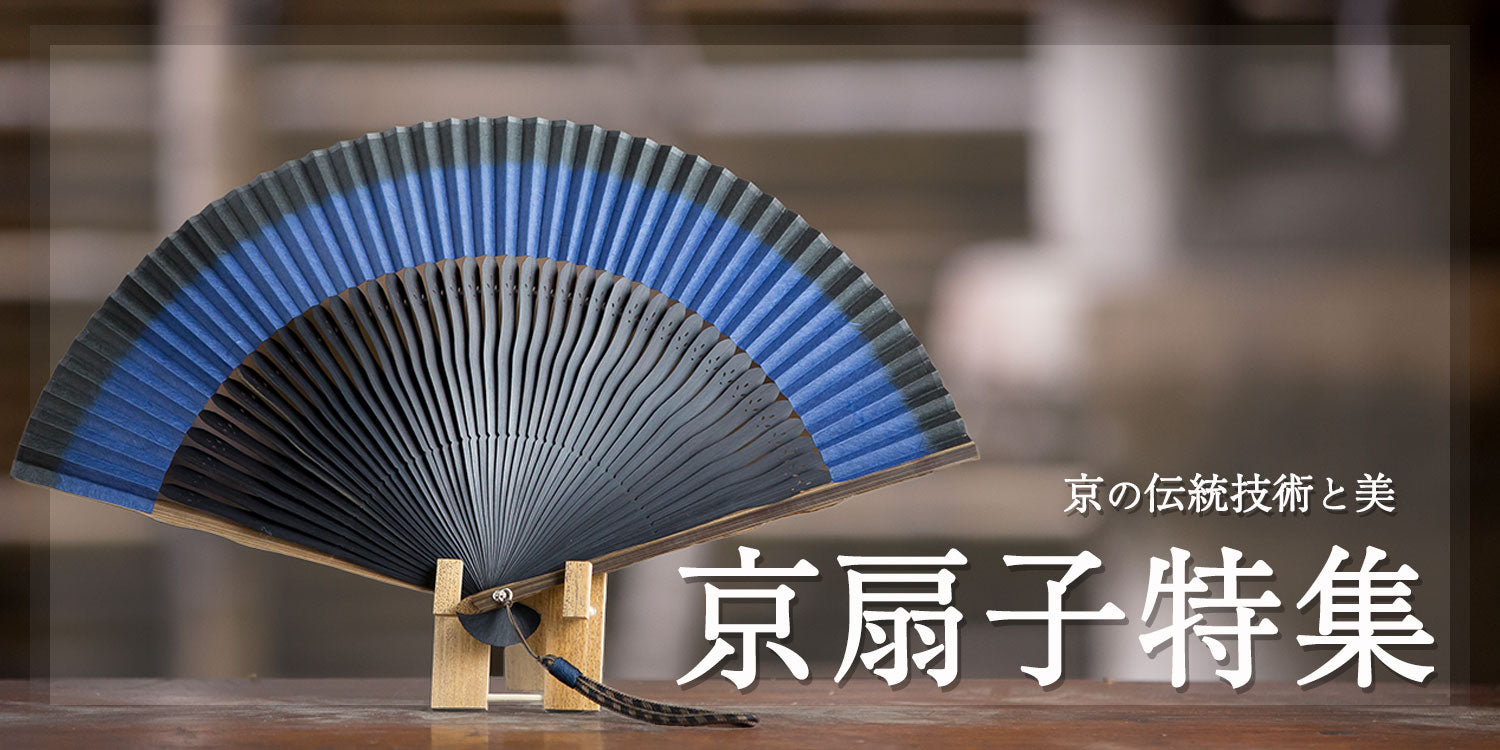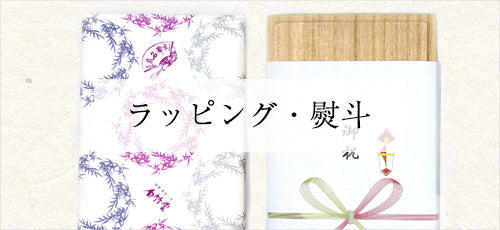日本では、昔から動物や虫、魚などに幸運や長寿など、特別な意味を見出し縁起物として大切にしてきました。今回は、扇子に描かれることの多い縁起の良い生き物についてご紹介します。柄に込められた意味を知ることで、贈り物としてプレゼントする際にもご活用いただければ幸いです。
縁起物の良い動物
縁起物として知られる動物には、古くから人々の願いや祈りが込められてきました。たとえば、長寿や平和、繁栄など、それぞれの動物にまつわる意味があり、扇子の柄としてよく用いられています。ここでは、扇子の意匠によく登場する代表的な縁起物の動物について、その意味も合わせてご紹介します。
鶴
「鶴は千年、亀は万年」と言われるように、長寿を象徴する動物。実際に千年生きることはありませんが、平均寿命は20年~30年と鳥類の中では長生きです。また鶴はつがいになると添い遂げると言われているため、夫婦円満を願う意味もあります。
左馬
「馬」の文字を左右反対で書いたものを「ひだりうま」と読みます。「うま」を逆から読むと「まう」となり、この読みが「舞う」を連想させることから左馬は招福を意味する縁起の良い文字とされています。また馬は右から乗ると転びやすく、基本的に左から乗ることから左馬は長い人生を転ぶ事無く過ごすことができるという意味もあります。
千鳥/波千鳥
千鳥:「千取り」の語呂合わせから「千の福を取る」という意味があり、勝負運の強さを表します。
波千鳥:波や水と共に描かれたものは「波千鳥」と呼ばれ、波を世間に例えて「荒波をともに乗り越えていく」ことを表すことから、夫婦円満、家内安全などの意味もあるとされています。
龍
龍は中国発祥の伝説の生き物。古くから水を司る神として祀られており、五穀豊穣を表します。また天に上る姿から、出世や成功など運気上昇の意味もあるとされています。
鳳凰
中国から伝来した伝説上の生き物で、おめでたい事が起こる前兆に姿を現すという言い伝えがあることで知られています。また古来より不死鳥であることから、成功や繁栄の象徴としても親しまれてきました。
猫
招き猫で知られるように、商売繁盛お金を招く縁起の良い動物とされています。また昔から猫が人間の作物を荒らすことなく、ネズミを退治してくれたことから家内安全の意味もあります。
縁起の良い魚
魚をモチーフにした柄も、扇子によく使われています。水の中をいきいきと泳ぐ姿は、見ていて涼しさを感じさせてくれるだけでなく、縁起の良い意味も込められ、贈り物にもよく選ばれる絵柄です。
金魚
中国ではお金が余ることを表す「金余」と言葉があり、この言葉が金魚の発音と似ていることから、金運上昇を招く生き物とされています。日本では、金魚の赤色から「魔除け」の意味を持つとされ、病気や災いから守ってくれるという言い伝えもあります。
鮎
古くは『日本書記』『古事記』にも登場しており、幸先のよい吉兆を表す魚として、日本人との関わりが深く愛されてきた川魚です。急流に流されながらも何度ものぼり続ける鮎は、困難を乗り越え出世するという意味から、立身出世の意味もあります。
縁起の良い虫
意外に思うかもしれませんが、虫にも縁起が良いとされるものがあります。日本では古くから、その姿や動きに意味を見出し、暮らしの中に取り入れてきました。季節を感じさせる虫のモチーフは、見た目の風情も感じさせてくれます。
蜻蛉
前にしか飛ぶことができず、後ろに下がれないことから、勝利を招く「勝ち虫」とも呼ばれています。戦で縁起を担ぐ戦国武将の間で好まれたデザインで、武具や装束などに取り入れられてきました。現代では剣道の道具などにあしらわれています。
蛍
古くから日本人に愛されてきた蛍は、平安時代の和歌に詠まれたり、『源氏物語』に登場したりなど、その儚く美しい姿から恋に重ね合わせられてきました。そこから幸せの象徴や恋の象徴として、意味を持つようになったと言われています。
蝶
サナギから脱皮して美しい蝶に生まれ変わるその神秘的な様から不死・不滅の象徴として、武士に好まれた絵柄です。平安末期の平氏一門がアゲハ蝶の羽を休める姿を描いた蝶紋をよく用いたことから平家の家紋としても有名です。
まとめ
扇子に描かれる動物や魚、虫たちには、涼し気な見た目だけでなく、昔から受け継がれてきた意味や願いが込められています。ひとつひとつの柄に込められた意味を知ることで、扇子の選び方にも少し深みが出てくるかもしれません。白竹堂では、昔から親しまれてきた柄を大切にしつつ、今の暮らしに合う扇子を取り揃えています。日常の中でさりげなく使える縁起物として、ぜひご覧になってみてください。